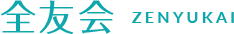弁護士 河津博史(かわつ・ひろし)51期
笠井治先生からお電話をいただいたのは、昨年の春、穏やかな陽気の日のことだった。直接お話しするのは何年かぶりのことで、その間、体調を崩されたとうかがっていたが、お元気そうな声を聞いて安心したことを覚えている。笠井先生のご用件は、名古屋大学出版会から刊行されている『法曹の倫理』の第4版の発行にあたり、笠井先生が第3版で執筆された刑事弁護の章について、改訂を手伝ってほしいというご依頼であった。もとより全友会の刑事弁護士の大先輩であり、理論家として知られる笠井先生のご依頼をお断りする理由はなかったが、丁度そのとき笠井先生と議論し、共同して執筆したいと思う弁護士倫理のテーマがあった。
そのころ、日弁連では「刑事弁護における真実義務」という弁護士倫理の古典的な論点について、従来の枠組みに疑問を提起し、これを大幅に見直すような議論が行われていた。この議論のきっかけとなったのは、『解説「弁護士職務基本規程」第3版』の改訂の検討作業である。
弁護士職務基本規程5条は、「弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする」と規定し、同82条1項後段は「第5条の解釈適用に当たって、刑事弁護においては、被疑者及び被告人の防御権並びに弁護人の弁護権を侵害することのないように留意しなければならない」と規定している。『解説』は、規程5条について、「実体的真実(客観的真実、事件の真相)の発見に積極的に協力する義務」を「積極的真実義務」と定義した上で、「刑事事件において被疑者、被告人の有罪を立証する義務はあくまでも訴追者である検察官に課されているのであり、弁護人にはそのような積極的真実義務は課されていない」としていた。その一方で、「弁護人といえども裁判所・検察官による実体的真実の発見を積極的に妨害し、あるいは積極的に真実を歪める行為をすることは許されない」とし、それを「消極的真実義務」と定義して、「弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない」と規定する弁護士職務基本規程75条が「この消極的真実義務があることを明らかにした」ものであると解説していた。『解説』が採用するこのような見解は、「消極的真実義務肯定説」と呼ばれている。
これに対し、「誠実義務純化論」と呼ばれる見解も、有力に提唱されていた。この見解は、弁護人の刑事手続上の責務は誠実義務に尽き、弁護人の本質は、被疑者・被告人の自己防御権を徹底的に擁護すべき用心棒(hired gun)であって、いかなる意味でも真実義務を負わないと説いた。ややアウトローな響きもあるこの見解は、熱心な弁護活動を行う刑事弁護士にとって魅力的に感じられるものである。
しかし、近年の日弁連における議論は、必ずしもこれらの見解の対立という形では展開されず、むしろ、これらの見解が共通して前提としているものに疑問が提起されていた。「被疑者、被告人の有罪を立証する義務はあくまでも訴追者である検察官に課されているのであり、弁護人にはそのような積極的真実義務は課されていない」「裁判所・検察官による実体的真実の発見を積極的に妨害…することは許されない」という表現に滲み出ているように、従来の見解は、有罪の立証・認定と実体的真実の発見を同視し、裁判所と検察官のみによって実体的真実が発見され得ることを前提としてしまっている。しかし、真実の発見には、犯人を処罰するという側面と、犯人でないものを処罰しないという側面がある。刑訴法は、そのような両側面を有する真実が裁判所と検察官のみによって発見可能であるという立場を採ってはいないはずである。そうであるにもかかわらず、真実の発見のために弁護人が果たすべき義務の存在を殊更に否定することは、適切ではないのではないか。この国の刑事司法の特徴である、弁護人を排除して行われる取調べ、罪証隠滅の防止を理由とする身体拘束や証拠開示の制限は、いずれも被告人・弁護人は検察官・裁判所による真実の発見を妨げる存在であるかのような偏った認識によって支えられている。従来の見解は、そうした偏った認識を助長しかねないものである。
また、「消極的真実義務肯定説」は、「消極的真実義務」の内容が明確でないことから、有効な行動指針を示すことができていないという問題意識も示されていた。「消極的真実義務」は「弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない」ことのみを意味するのか、そうでないとすれば「裁判所・検察官による実体的真実の発見を積極的に妨害し、あるいは積極的に真実を歪める行為」には何が含まれ、何が含まれないのか、共通の理解は得られていなかった。
このような疑問や問題意識に基づき、従来の「積極的真実義務」「消極的真実義務」という枠組みを見直し、刑事弁護における「真実を尊重」する義務の意義を再定義すべきであるという意見が、近年、支持を集めていた。
笠井先生は、『法曹の倫理』第3版において、「消極的真実義務肯定説」の立場を採られていた。もっとも、その前提として、弁護人の任務は自己防御を強いられた非力な存在である被疑者・被告人のために誠実かつ献身的に弁護活動をすることであり、刑事弁護における誠実義務には、献身すなわち被疑者・被告人のためにする情熱を内包する点に際立った特質があり、弁護人は被疑者のために情熱的な闘争的弁護(zealous advocacy)に努める義務を負うことが強調されていた。弁護人に被疑者・被告人に有利な真実の積極的追究義務は間違いなくあるものの、それは誠実義務の問題として捉えるべきであると論じられていた。そして、刑事事件における弁護人は、司法制度の一翼を担う重要な一員でありながら、制度上、被疑者・被告人の権利及び利益のためだけに活動を義務づけられた存在であるとし、これを、大野正男弁護士の「楕円の論理」を引用して、「2つの中心点は一点に重なる」と比喩的に表現されていた。
笠井先生からのご依頼は、『法曹の倫理』第3版の原稿に好きなように加筆してくれてもいいし、何だったら全部書き直してくれてもいい、というものであったが、私は、近年の日弁連における議論状況を踏まえて、「刑事弁護における真実尊重義務」の論点につき、笠井先生と議論し、共同して改訂を進めたいと考えた。
被疑者・被告人には自己防御権があり、自己負罪拒否特権が保障されているのであるから、検察官の有罪立証や裁判所の有罪認定に協力する義務はない。したがって、被疑者・被告人の自己防御権を実効化するために存在する弁護人にも、そのような義務のないことは明らかである。しかし、そのことを「積極的真実義務はない」と表現する必然性はない。民訴法においては、訴訟当事者の誠実義務の内容として、積極的に真実を陳述する義務という意味での「積極的真実義務」があるか否かが論点とされている。しかし、憲法で自己負罪拒否特権が保障されている刑事訴訟において、その意味での「積極的真実義務」の有無は論点とする必要性もない。
規程5条の「真実を尊重」する義務の意義について、同82条1項後段の規定を踏まえて解釈するにあたっては、刑訴法が明らかにしようとしている「真実」とはどのようなものであり、それはどのようにして明らかにされるべきものなのかを再確認する必要がある。「真実」の発見には、犯人を処罰するという側面と、犯人でないものを処罰しないという側面があり、それは決して前者のみを意味するものではない。そして、当事者主義訴訟構造を採用する現行刑訴法は、そのような「真実」は、検察官が適正な捜査を通じて収集した証拠により犯罪の証明を試み、被告人側が防御を尽くし、裁判所が公平な立場で事実を認定する手続により、明らかにされるという立場を採っている。特に後者の側面の「真実」の発見のためには、弁護人の役割が必要不可欠であり、弁護人は、被疑者・被告人のために防御を尽くす役割を果たすことを通じて、真実の発見に寄与することが予定されているのである。
とすれば、弁護人が被疑者・被告人のために防御を尽くすことは、被疑者・被告人に対する誠実義務の履行であるのと同時に、真実尊重義務の履行ともなり得る。誠実義務を強調するために、真実発見のために果たされることが不可欠な弁護人の役割を殊更に真実尊重義務と無関係なものと位置付ける必要はない。むしろ、検察官と裁判所のみが真実を発見する義務を負い、それによって真実が発見され得るものであるかのような整理をすることは不適切である。旧弁護士倫理7条は、「弁護士は、勝敗にとらわれて真実の発見をゆるがせにしてはならない」と規定していたことから、「真実の発見」は依頼者の権利利益の追求と相反する性質を有するもののようにも見えた。しかし、規程5条は「弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする」と規定しているのであるから、刑事手続において被疑者・被告人のために防御を尽くすことを通じて真実発見に寄与する弁護人の役割を積極的に位置づけるべきである。そのように位置づけてこそ、「楕円の論理」の「2つの中心点は一点に重なる」ことになると思われる。
刑訴法が「真実」は検察官が適正な捜査を通じて収集した証拠により犯罪の証明を試み、被告人側が防御を尽くし、裁判所が公平な立場で事実を認定する「手続」によって発見されるべきとする立場を採っていることからすると、その「手続」を害することが、「真実を尊重」する義務に違反すると理解すべきであろう。規程75条が禁止する「偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出」する行為は、正にその「手続」を害するものである。弁護人の陳述は規定75条の規律対象に含まれていないが、弁護人が「知っている」事実について虚偽の陳述をすることは、真実を発見するための「手続」を害するものであり、「真実を尊重」する義務に違反すると言うべきである。
ここで留意すべきなのは、弁護人が「知っている」ことと、弁護人が主観的心証を抱いていることは異なることである。弁護人は被疑者・被告人の自己防御権を実効化するために存在するのであるから、自らの主観的心証とは異なる主張・立証であっても、しなければならないことがある。裁判所が抱く心証を予測し、その主張・立証が被疑者・被告人の利益に適うかどうかを検討して、被疑者・被告人と協議を尽くす必要はあるが、それは誠実義務から要請される事柄である。弁護人の役割は被疑者・被告人のために防御を尽くすことであり、事実を認定するのは裁判所の役割なのであるから、弁護人がその主観的心証と異なる主張・立証をすることは、何ら真実を発見する「手続」を害するものではない。これに対し、弁護人が虚偽であると「知っている」主張・立証をすることは、「手続」を害するものであり、「真実を尊重」する義務に違反すると言うべきであろう。弁護人が事件そのものを直接体験して「知っている」ことは多くないが、手続上の事実や関係者が表明している意思については「知っている」ことがある。真実尊重義務により禁止されるのは、そのような「知っている」事実についての虚偽の陳述や証拠の提出であると考えるべきである。
私はこのような議論を笠井先生に投げかけ、意見交換を重ねることにより、この論点の検討を更に深めることを希望し、それを楽しみにしていた。しかし、その機会が訪れることはなかった。笠井先生の突然の訃報に接したのは、昨年7月、編者から正式な執筆依頼状も届かないうちのことであった。
その後、できる限り笠井先生の文章を残してほしいとの編者の要望を受け、第3版の原稿に加筆する形で改訂作業を行った。「刑事弁護における真実尊重義務」については、従来の議論の経過を記述した上で、近年の議論状況を踏まえた加筆をさせていただいた。「刑事弁護」の章を笠井先生と私の共同執筆という形で収録した『法曹の倫理〔第4版〕』は、今年8月に発行された。
刑事弁護士として数多くの無罪判決を導かれ、法科大学院での教育にも情熱を注がれた笠井先生は、刑事弁護の実務と理論の発展に多大なる貢献をされた。深甚なる敬意と感謝の意を表するとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げる。